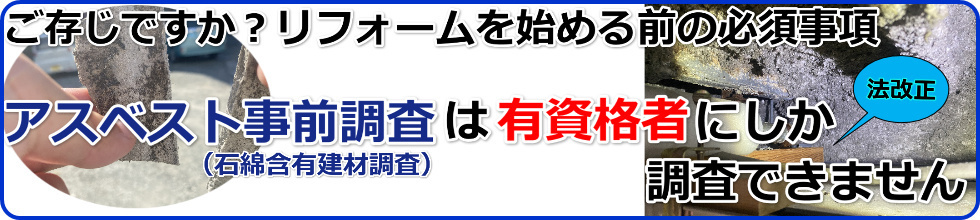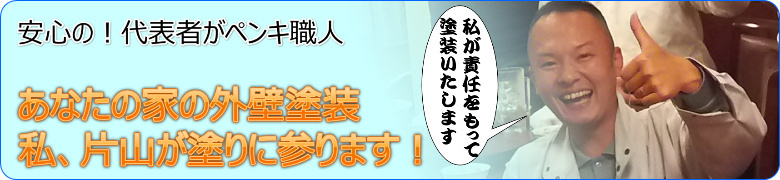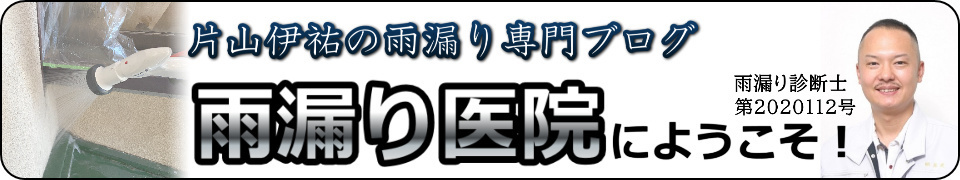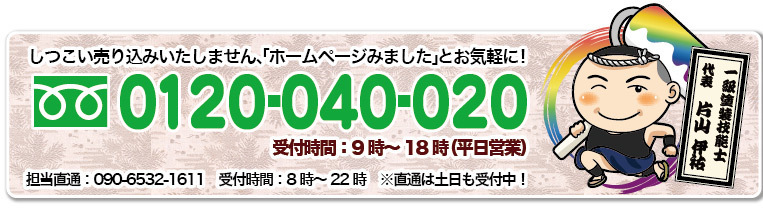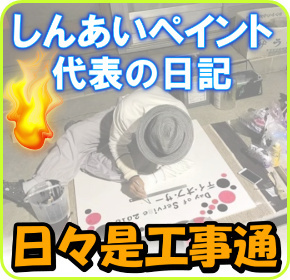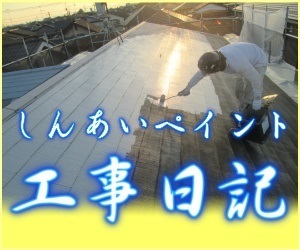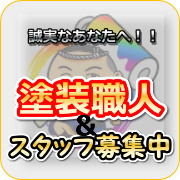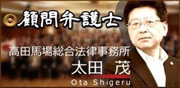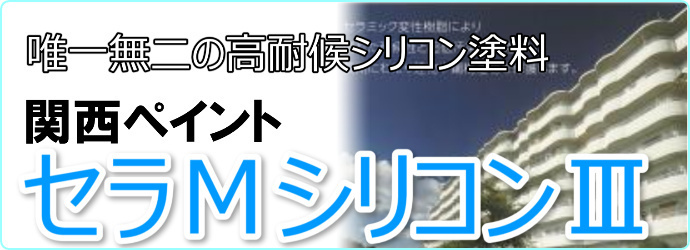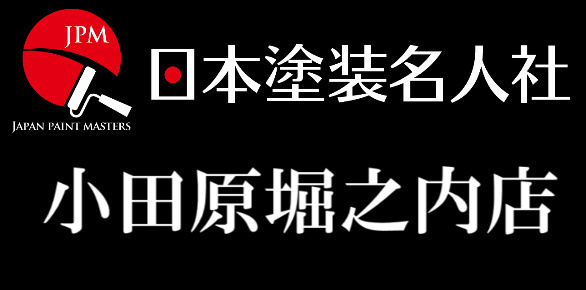【FROSIO表面処理検査員・雨漏り診断士・一級塗装技能士】が管理監修を行なう店
〒250-0853 神奈川県小田原市堀之内294-4
受付時間:AM8:00~PM19:00
塗装職人としてのこだわり
塗り替え工事には熟練の職人が付ききりで担当するのが当然で、手慣れたその仕事ぶりにはむしろ安堵のため息すら出てしまうほど。
一般的には『10年』という経験年数をして初めて職人と呼ばれる・・・・そう言われておりますが、私はそう思いません。
技術と経験を重ね、自分自身を磨きながら一日一日を大切な時間ととらえた職人であれば、5年でも10年でも職人と考えます。
逆をいえば長い年月を塗装に携わっていながらも、所属する塗装店の意向に沿った仕事ができない人もおります。
ましてやそこに、『工事代金を頂いている』という、お客様からの願いを託された立場でありながら
も期待にこたることができなければ、もはやプロフェッショナルとはいえません。
職人という生き方に誇りを持ち、誰からも後ろ指をさされない自信があればこそ、その人生を塗装という名の『作品』に込めることができるでしょう。
そもそも、塗装とは?
当サイトは時々同業種(他の塗装屋さん)の方も見て下さるそうで、「ホームページ見ました」とか「ずいぶん更新しているね」などとお声がけ頂いくこともあります。
塗装とは・・・・と、まだまだ若輩者の自分がいうのも恐縮ですが、外壁塗装をお考えの方へ対して、ごく一般的なことをできるだけ分かりやすくお伝えすることがこのサイトの主旨。
まずは塗装についてインターネット上の大辞典:Wikipediaより引用文を記載いたします。
塗装とは
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用塗装は、一般的に物体の装飾や保護、防錆を目的として行われるが、建築物などでは通路とそれ以外のスペースの識別などにも使用されることがある。なお、同様の目的でめっきを施すこともあるが、塗装の多くは表面に皮膜となる塗料を常温・大気下で塗布することができ、より簡便である。ただめっきに比べると塗料の性質上、強固な皮膜とはなりにくい。
金属の多くは大気中の酸素に触れることで酸化し錆を発生させるが、この鉄の場合は表面の錆が内部に向かって浸蝕する性質が強く、多くの鉄製品では塗装が必須である。また単純に見栄えを良くするための装飾の目的でも塗装はしばしば行われる。
塗料にも目的によって様々な性質のものがあり、防錆用に耐候性に優れ厚い皮膜を作るものから、装飾用に耐光性に優れ発色良く光沢ある表面に仕上がるもの、艶消しなど特定の性質を持つものなど様々である(→塗料)。これらには各々得手不得手があり、その目的に添って使い分け、或いは重ね塗りが行われる。また適切に重ね塗りすることで、単一の塗料では得られない強固で見栄えの良い塗装を行うことが出来る。
塗料と皮膜の平均的な厚さが同じ場合は、特に均一に施された塗装ほど長持ちするが、これは一度の塗布では難しい場合がある。このため単一の塗料でも重ね塗りする場合があり、その際には前回と同一の一定方向に向かって帯状に塗布していくのではなく、前回とは直角になる方向に塗布していくことで、塗斑を抑えることが行われる。
なお、塗装においては、塗装をする対象物の塗装面の材質に合った塗料を選ぶ必要があり、場合によっては、塗料の性質に合うように塗装面にシーラーを施すなどの下処理が必要となる。
上記で書かれている通り、塗装といっても様々な役割があり、多様性がございます。
中でも、錆(さび)の発生を防ぐことを前提とした『防錆塗装‐ぼうせいとそう‐』は、機能性のみが重視されています。
次にシーラーですが、密着性・塗装しようとしている下地そのものに適した材料を用います。
シーラーの他に、用途によりフィラー・プライマー・ヤニ止めなどがありますが、基本的な考え方はほぼ同じです。
そして装飾という分野ですが、この装飾性のある塗料を仕上げに持っていくことによって下塗りと一体化します。
▼大まかな流れ▼
| 主に鉄部 防錆塗装 ※錆固定剤・サビ止め等 (下塗りに同じ) |
| サイデイング・モルタル・木部・スレートなど 下塗り ※シーラー等 |
| 装飾性塗装 ※仕上げ材 ※各樹脂がある
|
| 塗膜形成!
|
要約すると、外壁などの被塗装物の下地状況によって下塗り材を選び塗布、そのあと然るべき仕上げ塗料で塗膜形成するということになります。
最も重要なポイントとして上記の下塗りと仕上げ塗料は、一体化していなければ無力と言え、相互扶助の関係でなければなりません。
以上が塗装(外壁塗装)についての基本的な考え方です。
表向き大事なこと〜美観性〜
塗装の定義の一つに、【美観性を追求する】ということがあります。
美観性とは文字通りその見た目のことを表しますが、塗装工事の場合若干異なったものになります。

新築後約10年で塗装することとなった下屋根

下地を傷めないよう配慮して塗り上げた下屋根

劣化した外壁(リシン壁)

強化工法により蘇った壁面(同リシン壁)
▲美観を追求するということは『見た目を良くする』こと即ち『活力を与える』ことに他なりません。
外壁塗装とは、工芸品のように新しく用意した素材などではなく、経年したもの‐つまり古くなった素材へ対する蘇生方法であることから、はじめに行う洗浄・乾燥、そして下地処理・下塗り・各仕上げ作業に至るまで、『蘇生』に重きを置かなければならないのです。
美観を良くするための道のりは、意外と奥深いといえるでしょう。
次に、表面的な美観を意識した施工技術にふれてみます。
職人技その1:ダメ込み

下塗り塗布後 天井のみ仕上がっている

職人技その1:ダメ込み(線出し工程)
▲上記画像は、天井の色と外壁の色を区分けするときの工法【ダメ込み】というもの。
刷毛で演出するラインを全て統一して塗ることにより、よりキレイに魅せるためのやり方です。
職人技その2:吹き戻し

壁面に入ったひび割れ『貫通クラック』

切削や充填など各工程を経た『均し処理』

職人技その2:吹き戻し
▲これは『吹き戻し』といって、既存の壁面などにクラック(ひび割れ)があった場合のボカシ工法です。
元々が模様付きの粗面である際、補修痕が目立ってしまうのを防止することを目的としています。
段取りが大変なのに加え、高度な技術が求められるため、この工法を採用する業者は少ないといえます。
職人技その3:塗り分け工法

既存の調湿タイル

断熱セラミック塗料による色変え(画像は欧風調)
▲元の色が暗かった室内調湿タイルを明るい色に変更させたもの。
何層にも塗膜をボカシながら、人工的にならないよう化粧していく工法です。
外壁タイル・サイディングボードなどにも適用可。
職人技その4:艶出し再生塗装

経年劣化したスレート屋根

職人技その3:艶出し再生塗装
▲傷んだ材質を塗装により再生する方法。
職人技・・・といってもこれは、見た目だけなら実際のところ素人さんにでも出来てしまいます。
では一体なにが職人技なのか?といいますと、隙間一本一本を丁寧に必要塗り回数塗布し全面を厚膜塗装することによって高密着+高耐久な品質へと仕上げていることに加え、実は下地処理にも時間をかけているのです。
次は、下地処理にスポットを当ててみたいと思います。
見た目だけでは知ることのできない『下地処理』
下地処理とは、先に述べました『活力を与える』ということなのですが、なにもツヤを出すことや美観を良くするためだけに必要なのではありません。
一年中紫外線や外気にさらされ、豪雨や強風など天敵に囲まれ続ける建物を、その脅威から守るためやらなくてはいけない工程があります。
屋根の場合
●亀裂補修 ●縁切り及びタスペーサー(排水) ●釘・ビス止め ●板金への各シーリング ●防錆 ●吸水の激しい材質への目止め ●漆喰補修 ●死膜除去 など
外壁の場合
●亀裂補修 ●各種シーリング ●通気排水 ●死膜除去 ●爆裂及び欠損部補修 ●材質強化 ●露出下地造膜 ●防錆 ●目止め ●目粗し ●既存シリコン除去もしくは専用プライマー ●器具周り防水 など
と、様々な種類がありますが、これらを総じて【下地処理】と呼びます。
四季を通じ、数々の困難を乗り越える必要のある建物だからこそ、下地処理が欠かせません。
以下に屋根・外壁塗装工事における下地処理の一例をご紹介いたします。
下地へのこだわり1:縁切り

屋根内部への雨水侵入を防ぐための『縁切り』

縁切りを確保するための『タスペーサー挿入』の最中
▲屋根の特性上、雨水が内側へ入り込みやすい角度(勾配‐こうばい‐)であることから、適宜排水箇所を設けることが重要です。
もしも雨が内側へと入り込んでしまった場合、屋根の裏側(防水シートないし野地板‐のじいた‐以降)へと浸水してしまうため腐食し、さらにはシロアリや腐朽菌の繁殖へとつながってしまいます。
縁切りを分かりやすく言えば、「水の逃げ道を作っておく」・・・・ということ。
このような考えから上記作業は必須工程となっています。
下地へのこだわり2:防水処理

破風板などのジョイントに空いた隙間を埋める

板金を固定する釘そのものをシーリングで防御する
▲ こちらは排水とは真逆の発想で、防水を意味します。
当工程を行う第一の理由は、経年によって継ぎ目の開口/板金の釘が浮いてしまう為、空いた隙間から水が入るのを防止する役割があること。
そして第二の理由は、台風などの吹きあがる強風から板金が剥がされ、飛ばされてしまう前に固定する意味が込められています。
こちらも必須となります。
下地へのこだわり3:亀裂補修

貫通クラック・拡張

下塗り塗布

ひび割れ防止材充填(複数回)・硬化後・逆プライマー塗布
▲ひび割れ部分への再発防止・塗料密着強化・汚染防止対策。
これは構造上避けられないクラックへの下地処理であり、深く割れている『貫通クラック』への必要不可欠な工程となり、モルタルやパテなど粘度のないものを用いても全く意味がありません。
適したものを最良の手順で行う事こそが本来の下地処理であり、手を抜くことは絶対に許されないのです。
(これと似たものに『ヘアークラック』があり、これは収縮運動などで建材の表層のみが割れてくる現象をいいます)

ご紹介した例はほんの一部にすぎませんが、比較的分かりやすくご理解頂けそうなものをまとめてみました。
では、下地処理を行わない場合どのように変化するのでしょうか?
漏水対策をせず放置された例で、工事のとき特に雨漏りがひどかったものを特定・発見した時のものを参考に解説してみます。

天井裏に何らかの圧が掛かり、大きな亀裂が入っている

構造上、上部に雨水が溜まる可能性があったため赤外線カメラで確認・切り込みを入れてみる

排水
▲天井裏に存在していた雨水を掻き出した時のものです。
下地処理(防水)さえ行っていれば防ぐことができた、典型的な雨漏り事例。
内部からわかる場合と、そうでない場合があるのは構造上致し方ないことではありますが、これらを未然に防ぐために下地処理が欠かせないのが現状です。
おわりに
長々とした文にここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
ご存知かとは思いますが、塗り替え工事を行うのは塗装業者の役目です。
どこのハウスメーカーでもリフォーム会社でも、こと塗装工事におきましてはペンキ職人が活躍いたします。
しかし漏水事故を防止できるのは、水の流れを知り尽くした職人施工店に限られてしまいます。
残念なことに只の塗り替え工事では、雨漏りを止めることができないのが実際の所。
これからの時代、防水と塗装分野は合併していくことが予想され、別の業種である限り雨漏りや塗膜剥離という、『防げるはずの事故』を減らすことはできません。
職人は毎日が勉強であり、現場作業で自身のスキルを磨くこと以外、お客様に高品質な工事を届けることはできないのです。
せっかくのリフォーム工事でいらぬ欠陥を出すことのないよう、限界まで知恵と技能を身に着ける必要が職人にはあります。
わたし達職人施工店であるしんあいペイントは、手掛けるすべての建物を雨漏りや紫外線劣化などから守り切る自信があります。
その根拠は、多くの事例をこなし日々の生活を防水塗装に費やしているからであります。
一度に複数の物件を手掛けません。
「その一軒に全身全霊を注ぐ」、これに尽きます。
お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:AM10:00~PM18:00
| 対応エリア | ●小田原本店は小田原市を中心に約一時間圏内を目安にしています 『小田原市/箱根町/南足柄市/山北町/開成町/松田町/秦野市/大井町/中井町/大磯町』 ●東京出張所は東京23区西部を中心に約一時間圏内を目安にしています 『世田谷区/杉並区/中野区/新宿区/練馬区/板橋区/豊島区/目黒区/小金井市/三鷹市/武蔵野市/西東京市』 |
|---|
代表の片山です
施工(塗装工事)について
以下、施工方法や施工時における注意点を記載しております。↓ ↓ ↓ ↓
足場
水洗い
養生〜マスキング〜
屋根塗装
外壁塗装
基礎部分
シーリングについて
付帯部
内装



施工エリア
小田原市を中心に約30分圏内を目安にしています
箱根町/南足柄市/山北町/開成町/松田町/秦野市/大井町/中井町/大磯町/