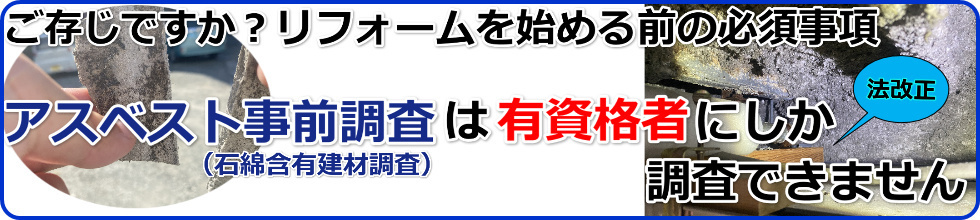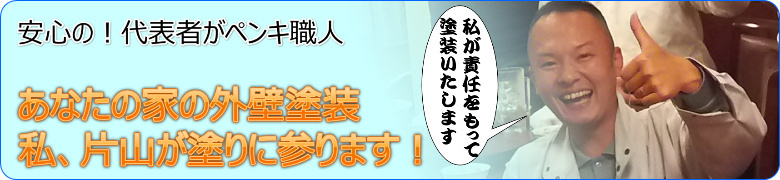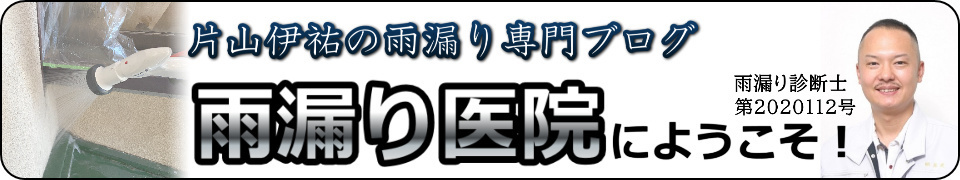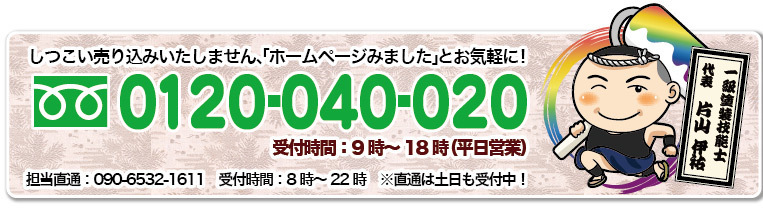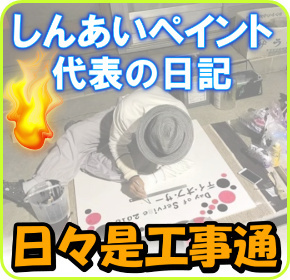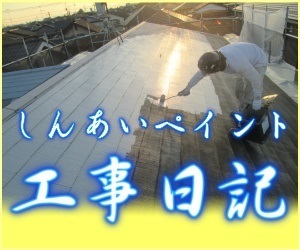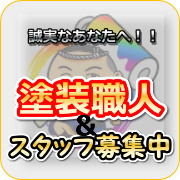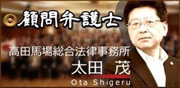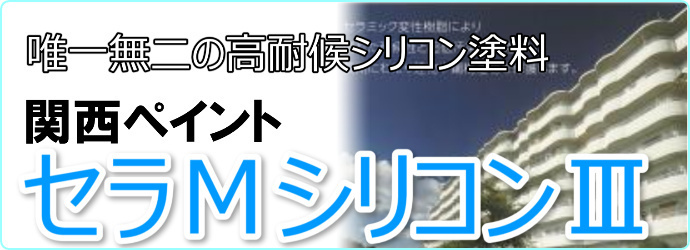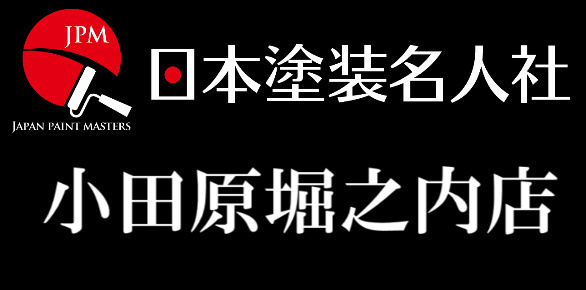【FROSIO表面処理検査員・雨漏り診断士・一級塗装技能士】が管理監修を行なう店
〒250-0853 神奈川県小田原市堀之内294-4
受付時間:AM8:00~PM19:00
雨戸の塗装
雨や風から窓ガラスを守ってくれる【雨戸】──。
普段使う機会が少なくても、台風のような荒れた天気の時には、特に利用されるかと思います。
そんな雨戸ですが、新築時には既製品(出来合いのもの)として工場出荷され、家のサッシ枠などにはめ込まれているはずですが、経年によって初期コーティングが劣化している事例が多くみられます。

築10年以上経過したものは変色や退色をしている場合が多く、設置場所によってはサビの発生もあるかもしれません。
劣化した状態が長く続きますと、雨戸表皮の落下や穴が開いてしまうこともありますので、定期的なメンテナンスが必要となってきます。
雨戸の種類
住宅の雨戸の中で、多く使用されているものが以下のような2つの種類となります。

①金属系雨戸

②木製の雨戸
この2種類の大きな違いとして
①[金属系のもの]
-
サビが発生する
-
熱伝導度が大きいため太陽光の影響が顕著に出る
-
塗料を吸い込まない
②[木製のもの]
- 雨水で腐食する
- 熱伝導度が小さいため外気の影響を受ける速度が遅い
- 引火しやすい
- 塗料を吸い込む
という大きな差があります。
つまりその性質上から『塗装方法の違い』『使用すべき塗料の選択』が変わってきます。
「その塗料が適しているか」「どう塗るのか」「何のために塗るのか」が前提となり、素材・環境・条件に適したもので施工する必要があるのです。
雨戸塗装の流れ
ここでは、金属系の雨戸塗装の例を挙げてみたいと思います。

①施工前

②研磨
(死膜は除去する)

③下塗り
(高密着型プライマーを使用)

④中塗り
(遮熱フッ素使用)

⑤仕上げ塗り
(光沢を出すため厚塗り推奨)

⑥完了
金属系の雨戸は、降雨などが原因でサビの発生が起きやすく、酸化を防ぐために塗膜で覆うことが大切です。
また、直射日光が当たっている場合、熱伝導の働きからとても熱くなってしまいます。
ということは熱エネルギーを受け続けているわけですから、完成した塗膜自体の劣化速度がより早くなってきてるといえます。
そのような環境下に置かれた金属雨戸には、普通の塗料を塗るべきではないと考え、
-
遮熱
-
断熱
-
高耐候塗料
での施工が望ましいと言い切ることができます。
木製雨戸の場合ではどうでしょう。

『木』は水分を吸収する材質であるため、含水しない下地形成が求められます。
水を含まない=腐らない、という原則があるように雨水などを吸収しなければ木は腐りません。
それにしたがい塗料選びには『浸透型』+『造膜型』を選択することが大事で、ここさえ抑えておけば材質そのものを長持ちさせることが可能となります。
また、含水後3日間ほどは塗膜はく離を起こしてしまうため塗装ができず、施工方法にも注意を払わなければいけません。
雨戸などの付帯部では、表面を塗膜で守ることでしか防衛手段がありません。
金属系・木製問わず、使用する仕上げ塗料には高耐候・遮熱・断熱のいずれかを選択することがとても重要です。
逆をいえば、高耐候性のある塗料以下は使用しない方が良いといえるでしょう。
お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:AM10:00~PM18:00
| 対応エリア | ●小田原本店は小田原市を中心に約一時間圏内を目安にしています 『小田原市/箱根町/南足柄市/山北町/開成町/松田町/秦野市/大井町/中井町/大磯町』 ●東京出張所は東京23区西部を中心に約一時間圏内を目安にしています 『世田谷区/杉並区/中野区/新宿区/練馬区/板橋区/豊島区/目黒区/小金井市/三鷹市/武蔵野市/西東京市』 |
|---|
代表の片山です
施工(塗装工事)について
以下、施工方法や施工時における注意点を記載しております。↓ ↓ ↓ ↓
足場
水洗い
養生〜マスキング〜
屋根塗装
外壁塗装
基礎部分
シーリングについて
付帯部
内装



施工エリア
小田原市を中心に約30分圏内を目安にしています
箱根町/南足柄市/山北町/開成町/松田町/秦野市/大井町/中井町/大磯町/