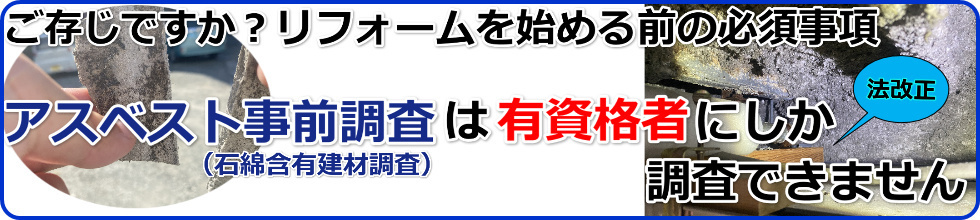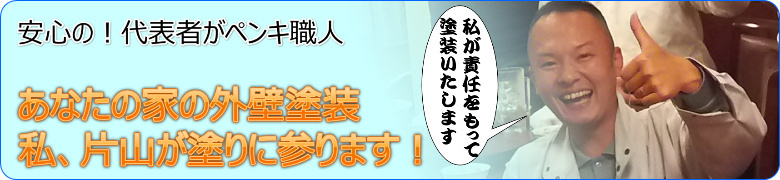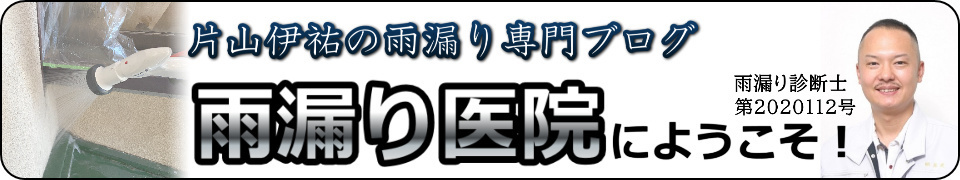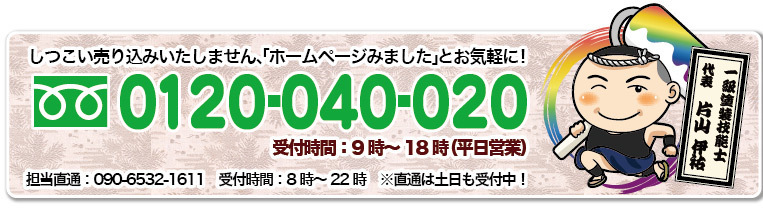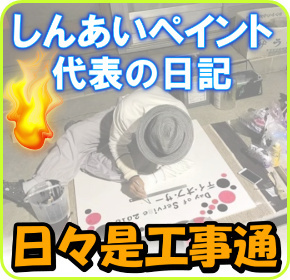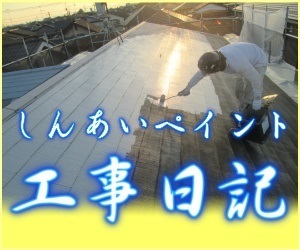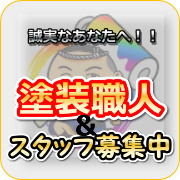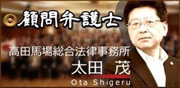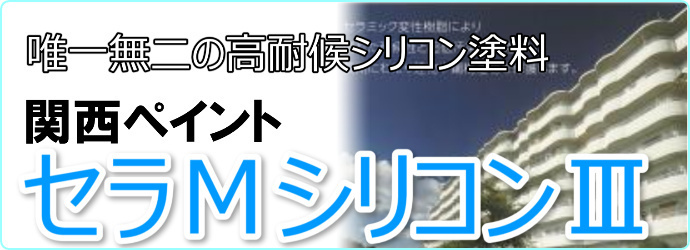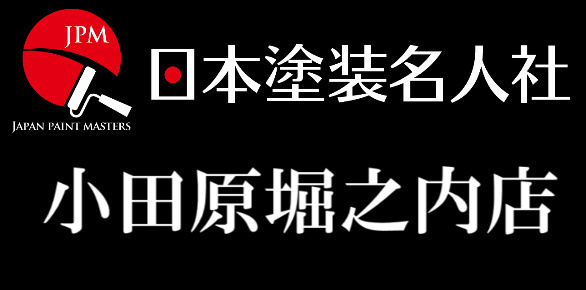【FROSIO表面処理検査員・雨漏り診断士・一級塗装技能士】が管理監修を行なう店
〒250-0853 神奈川県小田原市堀之内294-4
受付時間:AM8:00~PM19:00
施工不良その2 水をため込んだ防水層
漏水を防ぐためにある【防水】
本来、抜群の防水効果のあるものですが、新築時または改修工事の際、施工する職人さんのやり方次第では時として仇となる事があります。

工事途中の養生テープを貼ったベランダ防水
画像ピンク色のものは養生用のガムテープ(上の外壁を塗装するためのマスキング)、塗り替え工事のワンシーンです。
一見何の変哲もないベランダ防水の状況ですが、いつもの勘が働きました。

指で押している部分は『立ち上がり』 風船のような感触
ベランダ床から外壁にかけて立ち上がっている部分に違和感を覚えました。

切り込みを入れ、排水を促してみる

大量に出てきた液体。このような状態にも気が付く・気が付かないは職人次第
ここで無視してしまっては建物の為にならないので急遽切り込みを入れることにした所、案の定出てくる雨水。
しかもそれはヌメリを伴っている水です。
性質が変わってきている確たる証拠。
『防水層の中に入り込む雨水』というのは、ちょっと考えものです。
なお、当概住宅はコンクリート造でしたのでこのまま放置は不親切であることから、一旦撤去することにしました。

めくってみると残念な結果に
剥がした防水の裏にあるのは、旧壁面でした。
おそらくは一回前の塗り替え工事の時に、防水床をかさ上げしたものと思われます。
これは非常に危険な施工法であります。
まず最も重要な、【水切り】がないのは残念ですね。
そして立ち上げた防水(今回剥がした部分)と外壁の境目にはシーリングのみが打ってあり、一旦すき間が開いてしまえば雨水の侵入経路が確保されてしまいます。
これでは経年考慮がなされていません。
やはり施工業者としては1次防水のみならず、最低限2次防水のことまでは工事科目に入れておくべきであると言えます。
このように、何年もたってから露見してくる非常に厄介な事例があとを絶ちません。
新築工事をはじめリフォームや塗り替え工事に至るまで、行政主導のもと採点制度等何らかのペナルティを採り入れなければ、この業界特有の「その場さえ良ければそれで良し」という悪習は無くなることはないでしょう。
お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:AM10:00~PM18:00
| 対応エリア | ●小田原本店は小田原市を中心に約一時間圏内を目安にしています 『小田原市/箱根町/南足柄市/山北町/開成町/松田町/秦野市/大井町/中井町/大磯町』 ●東京出張所は東京23区西部を中心に約一時間圏内を目安にしています 『世田谷区/杉並区/中野区/新宿区/練馬区/板橋区/豊島区/目黒区/小金井市/三鷹市/武蔵野市/西東京市』 |
|---|
代表の片山です
施工(塗装工事)について
以下、施工方法や施工時における注意点を記載しております。↓ ↓ ↓ ↓
足場
水洗い
養生〜マスキング〜
屋根塗装
外壁塗装
基礎部分
シーリングについて
付帯部
内装



施工エリア
小田原市を中心に約30分圏内を目安にしています
箱根町/南足柄市/山北町/開成町/松田町/秦野市/大井町/中井町/大磯町/