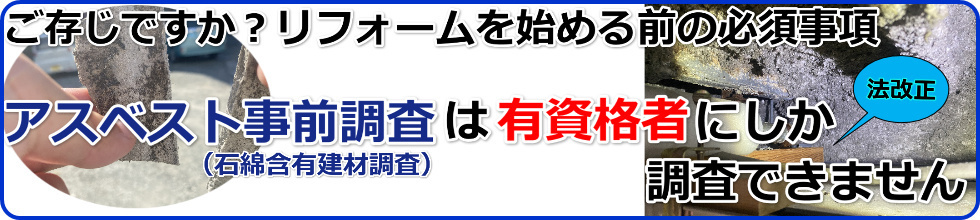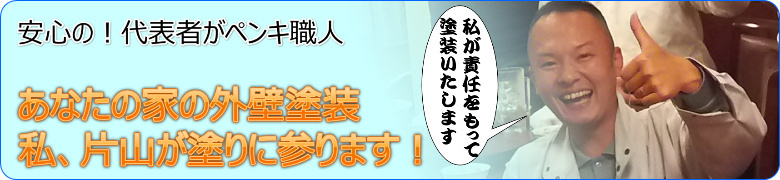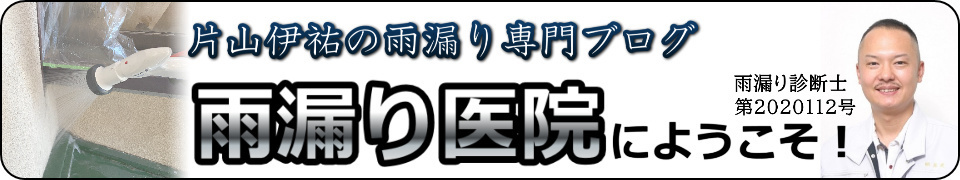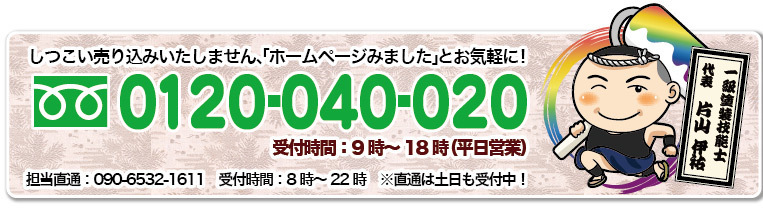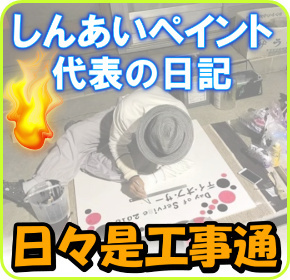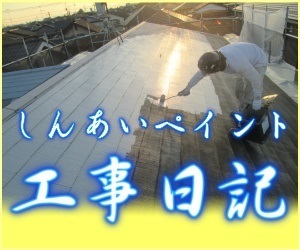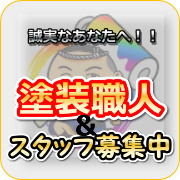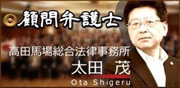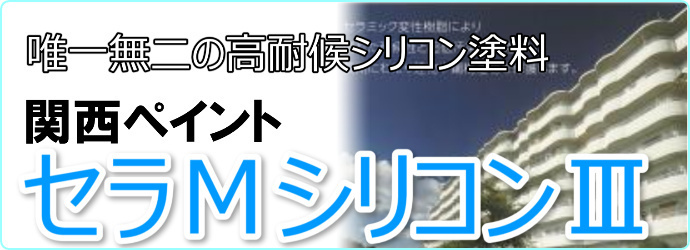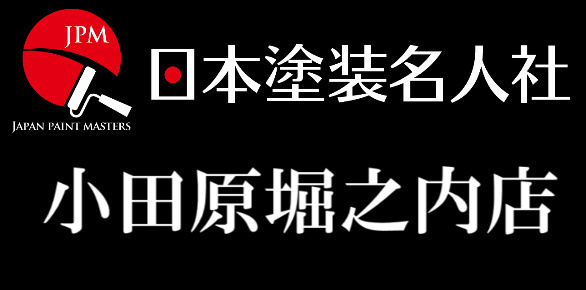スレート屋根の縁切り作業
2018.4.2 月曜日
国内における住宅の屋根。
以前は日本瓦が多く見られましたが、「地震の時に屋根の重みを減らした方が良い」という観点からか、ここ最近ではスレート屋根が主流となっています。
塗替え工事におけるスレート屋根といえば【屋根の内部結露】【毛細管現象による雨漏り】などの被害が多く、ただ単に色を塗るだけの塗装だけではダメだと、周知されるようになりました。

スレート屋根全景(一例として)

間近から見たスレート屋根
スレート屋根にはいくつもの種類(商品名・形状)があり、その施工方法や適した塗料などに違いはあるものの、大まかにはスレート屋根という呼び方で通ります。
今回はそのなかでも【ランバート】という種類の屋根を塗装しております。
一般的なスレート材では比較的やりやすく感じているのですが、このランバート(小割一文字葺き)の場合では難易度が高くなります。
理由は、その形状にあります。

① ランバートの形状

② 一般的に多く使われている屋根材(例:コロニアル)
②一般的なスレートには基本的に『横に走る目地』が多いのに比べ、①ランバートには『タテ・ヨコに目地』があるのがわかると思います。
そして、斜めになったりしている『ヨコの目地の形』もやりづらさに拍車をかけています。
初めての塗替え工事であれば、何の問題も無く塗装できてしまいますが、今回は2回目の塗替え。
先週の雨天もさることながら、前回の業者さんの施工方法によりある問題が発生してしまい、施工期間が延びてしまいました。
前回の工事では『タスペーサー未挿入』に加え、屋根材同士の重なり部分を塗料でふさぎっぱなしでで、縁切り作業なども確認できません。
結果、ランバート屋根の裏側にまで雨水が遡上-そじょう-してしまい、含水によりスレート瓦の耐久性はずいぶん弱いものとなっておりました。
今回の工程はというと、高圧洗浄〜乾燥3日間〜強化プライマー〜遮熱中塗り、ここまではスムーズに行ってきましたが、問題はここから始まりました。

施工前のようす
本来開いてあるはずのすき間は完全に塞がっている

中塗りを終え、現在のようす
丸囲み部分、施工前から何も変わらず、重なり部分は密着したまま。
このままでは漏水や腐食の原因を放置することになるため、【縁切り】という作業に入ります。

工具を差し込み、矢印の部分にも切り込みを入れる

緑の矢印箇所には【タスペーサー】が挿入されている

適切なすき間の確保に成功
ここまでの流れが、縁切りと呼ばれる防水対策の一環。
すき間を確保することで毛細管現象による、雨水の浸入経路を絶つことができるのです。
普段では、縁切り作業は早めに終えることができるのですが、複雑な形状のランバートであることと、今回は以前に塗られた塗膜の厚みが瓦内部まで入り込んでいて、とてつもなく堅く、作業に時間を要しました。
ここまでやってから、ようやく仕上げ塗装に入ることが可能となります。
ちなみに、縁切り作業で多く見られる失敗事例に、瓦の破損があります。
スレート材は軽さが売りであるため、その分割れやすいのが弱点。
今回は旧塗膜がすき間の奥へと入り込み、内部でカチカチに固まっていたため縁切り方法にちょっとした工夫を致しました。

ハンマーで少しずつ差し込む
工具の先端と屋根材の接地面を大きくし、過度に衝撃を与えないように注意を払い縁切りを行ったため、時間はかかりましたが特別アクシデントもなく当該作業を終えることができました。

北側の屋根
家全体の、すべての瓦屋根に上記もしくは同じような工程の縁切りを行いました。
| 内容の近い記事 |